■ ぬいぐるみの・・・
藤田 博
ぬいぐるみには決まって縫い目があります。どれほどほんものらしくつくられていても、ほんものではない、ほんものに似せた「似せもの」であるのがわかるその縫い目は、うそとほんとの境目を示しています。うそのぬいぐるみが、ほんとになることがあるとしたらとの問い掛けは、話さないぬいぐるみが話し出す、動かないぬいぐるみが動き出すとしたらを問うことと一つです。話すのは持ち主が問い掛け、自ら答えるから、動くのは持ち主が動かしてやるから、そうしたことを承知の上で、なおかつそれを問い掛けなければならないのです。

A.A.ミルン『くまのプーさん』では、プーはもちろんのこと、コブタもイーヨーもカンガもルーもトラーもぬいぐるみ、ウサギとフクロ、そして言うまでもなくクリストファー・ロビンを除いてぬいぐるみです。ぬいぐるみであるために「脳みそ」を持たないプーは、頭が悪い。あたり前のそのことにプーは言及します。「ばっかなクマのやつ!」「ぼくは、とっても頭のわるいクマなんだ。」プーはいくつもの失敗を仕出かします。これを「失敗物語」と呼んでもいいほどです。しかし、プーは本当に頭が悪いのでしょうか。プーはいくつもの「発明」をし、いくつもの「発見」をします。頭が悪いとされるのは、そうしたものが常識を超えてしまっているからなのです。
読者はプーがぬいぐるみであることを忘れています。ぬいぐるみであるのを思い出すとすれば、クリストファー・ロビンが仲間の一人となっているのを意識する時です。そのロビンは、ぬいぐるみであるのを忘れさせることにもつながっています。プーはロビンのぬいぐるみ、ぬいぐるみの持ち主ロビンその人が、プーがぬいぐるみであるのを忘れているからです。そのためにこそ、ロビンは森に一緒に住むことができるのです。

ミヒャエル・エンデ『カスペルとぼうや』のぬいぐるみは、色々な模様の布でできた道化のカスペルです。カスペルはぼうやのお気に入りでした。ところが、おもちゃ屋のウィンドーをのぞき、一人で歩くロボットや口をきく人形を見たぼうやは、カスペルがつまらなくなり、窓から放り出してしまいます。イヌにくわえ上げられたカスペルは、かまれたり、ふり回されたり。すっかりきたなくなってしまったカスペルは、イヌの飼い主にぼろきれ扱いされ、ごみ入れに捨てられてしまうのです。くずやがそれを拾います。くずやの車の一番上にぼろの人形を見つけたのは、ぼうやのおばあさんでした。おばあさんには、ぼうやのカスペルであるのがすぐわかったのです。おばあさんは箱の中の箱の中の箱と七重もの入れ子にしたカスペルを送ります。そうしたのは、ほんものとは何かをぼうやに教えるためだったのではないでしょうか。
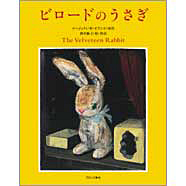
マージェリィ・W・ビアンコ『ビロードのうさぎ』にあって、ぼうやのお気に入りはうさぎのぬいぐるみです。ぼうやが新しいプレゼントに夢中になったために、子ども部屋の棚の中で暮らすようになってしまいます。お手伝いのナナが、イヌのおもちゃが見当たらないことから代わりにうさぎをあてがいます。ぼうやとまた一緒に過ごすようになったうさぎは、ぼうやにかわいがられ、よごれてきたなくなりました。「どこがいいんだろ、こんなきたない おもちゃの」と言うナナに、ぼうやは答えます、「この子は おもちゃじゃないの、ほんとうの うさぎなの」と。よごれていればよごれているほど価値がある、それが「子どもへやのまほう」なのです。
ぼうやが病気になりました。病気が治った後、「こりゃあバイキンのかたまりだよ。すぐにでも やいてしまいなさい。」と医者が言います。うさぎの頬を伝い、ほんとうの涙が地面に落ちます。にせもののぬいぐるみからほんものの涙が落ちたのです。そこに現れた妖精によって、うさぎはほんもののうさぎになることができました。ある時、ぼうやは、森の中でじっとこちらを見つめているうさぎと出会います。うさぎがその目で語ろうとしたのは何だったのでしょうか。ぬいぐるみのままでいたかったとの思いでしょうか。にせものはどこまでも似せたもの、ほんものになることのない「似せもの」です。それがほんものになるとはどういうことなのかを、うさぎは教えてくれているのです。
※A.A.ミルン・作/石井桃子・訳「くまのプーさん」(岩波少年文庫)
※ミヒャエル・エンデ・文/ロスビータ・クォードフリーク・絵「カスペルとぼうや」(ほるぷ出版)
※マージェリィ・W・ビアンコ・原作/酒井駒子・絵・抄訳「ビロードのうさぎ」(ブロンズ新社)
(英語教育講座)