歴史のなかの教科書
ポスター
パンフレット
問い合わせ先:宮城教育大学附属図書館
学術情報管理係 022-214-3348
※画像・文章の無断転載は、ご遠慮ください。
宮城教育大学創立50周年記念展示
「歴史のなかの教科書-思い出の教科書との再会-」
第2部
教科書のなかの児童文学―教材の原作にふれてみよう
展示監修・解説執筆: 中地文(宮城教育大学国語教育講座 教授)
● 1946~1960年代
ここでは、小学校国語教科書に焦点を当て、児童文学を原作とする教材の変遷をたどる。その出発点は、1946年に文部省が新教科書完成までのつなぎとして発行した、いわゆる「暫定教科書」である。従来の教科書に修正を加え、一部の教材の削除と補充を行ったというこの教科書に、アンデルセン「みにくいあひるの子」や宮沢賢治「どんぐりと山ねこ」(題名の表記は教科書に従う。以下同じ。)など児童文学を原作とする教材が新たに掲載された。編集を担当した石森延男によると、「日本の少年少女たちの心に光を与え、慰め、励まし、生活を見直すような教材」(「「麦三合」の思い出」)を選んだという。これらの教材は、多少の手入れが行われたうえで、1947年度に刊行された第六期国定教科書に引き継がれていった。
その後、1949年度から検定教科書が使用されるようになるが、1950年代の物語教材は、「有名な文学作品」(『文部時報』1948年5月)を選んだという第六期国定教科書の傾向を概ね踏襲している。アンデルセン、小川未明、浜田広介、宮沢賢治の童話の教材化が目立つほか、デフォー「ロビンソン・クルーソー」やコッローディ「ピノチオ」など、「名作」の名で出版されていた作品が教材化された。
なお、この時期に、現在も教科書に採録されている椋鳩十「大造じいさんとがん」(1950年に「がん」の題で初掲載)や、新美南吉「手ぶくろを買いに」、「ごんぎつね」が登場してきたことも注目される。作品「手ぶくろを買いに」は、当時『日本名作童話集』(主婦の友社、1948年)に収録されていたが、このことから考えると、南吉童話の教材化にも名作という発想が関わっていたのかもしれない。
1960年代に入ると、ウィーダ「フランダースの犬」やシュピーリ「アルプスの少女」など、世界の名作にもとづく教材が依然として見られる一方、小川未明、浜田広介、宮沢賢治、新美南吉に加えて、鈴木三重吉、千葉省三、坪田譲治といった日本近代児童文学作家の作品を原作とする教材が増えてくる。また、石井桃子、神沢利子、中川李枝子など、現代児童文学作家の名も少しずつ教科書に顔を出し始めた。
そのほか、50年代の児童書出版界の成果が教科書に表れてきたことにも留意すべきであろう。1953年より石井桃子、光吉夏弥等の編集によって出版された「岩波の子どもの本」は、絵を多く入れて日本の昔話や童話を提供するとともに、欧米の優れた絵本を紹介したことで絵本界に大きな影響を及ぼしたシリーズであるが、これを原作に持つ教材が生み出されている。マンロー・リーフ「花のすきな牛」やエッチ・エイ・レイ「ジョージのペンキぬり」、阿川弘之「きかん車やえもん」などである。これらは70年代以降に進められる絵本の教材化の先駆けであるともいえるだろう。
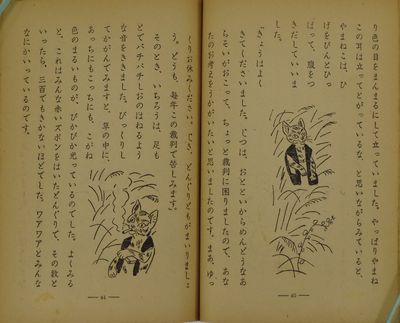
文部省著 『国語』 第4学年下、日本書籍、昭和22年(1947)検査、昭和23年発行
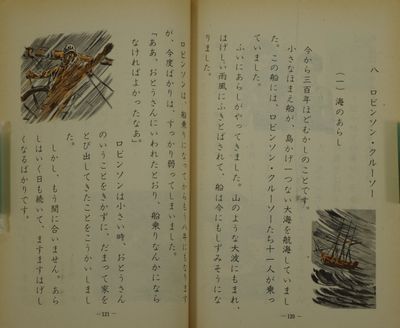
西原慶一他著 『国語の本』 小学第4学年前期用、二葉、昭和27年(1952)検査、昭和29年発行
● 1970年代~現在
1970年代に国語教科書のなかの物語教材が大きく変わったということは、向川幹雄氏や府川源一郎氏によって指摘されている。現代児童文学作家の作品を原作とする教材が続々と登場してくるというのである。あまんきみこ「白いぼうし」、安房直子「きつねの窓」、いぬいとみこ「長い長いペンギンの話」、今江祥智「三びきのライオンの子」、今西祐行「一つの花」、斎藤隆介「モチモチの木」、佐藤さとる「だれも知らない小さな国」、古田足日「大きい一年生と小さな二年生」、松谷みよ子「やまんばのにしき」などがそれにあたる。レオ・レオニ「スイミー」をはじめ、絵本の教材化も、この時期に進んだ。
教材化される宮沢賢治の作品が変わるのも70年代である。「やまなし」「注文の多い料理店」が新たに教材化され、50年代から掲載されていた「気のいい火山弾」(初期には「べご石物語」の題で掲載)や60年代から掲載されていた「けんじゅう公園林」は70年代後半以降消えていった。これは、道徳的な読解を要請する教材から表現の魅力を味わう教材への変化と捉えることができるだろうか。
以後、1980年代には角野栄子「サラダでげんき」、灰谷健次郎「ろくべえまってろよ」、山下明生「島引きおに」などが、1990年代には那須正幹「そうじ当番」、森山京「いいものもらった」などが、2000年代に入ると木村裕一「あらしの夜に」、宮西達也「ニャーゴ」などが教材として加わって現在に至っている。鈴木三重吉「少年駅伝夫」は74年を最後として、小川未明「野ばら」は89年を最後として教科書から消え、物語教材の原作は、宮沢賢治と新美南吉などを例外として近代児童文学から現代児童文学に移った。
とはいえ、興味深いのは2010年代に入って坪田譲治、浜田広介の作品が20数年ぶりに教材化されていることである。この近代児童文学作家復活の動きが今後進んでゆくのかどうか、注目したいところである。
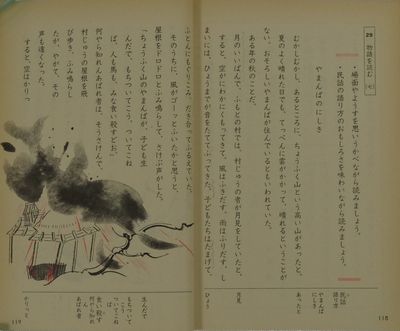
山本有三他著 『小学国語』 4下、日本書籍、昭和45年(1970)検査、昭和46年発行

中田祝夫他著 『小学国語』 2年上、日本書籍、昭和54年(1979)検査、昭和55年発行
【参考文献】向川幹雄『教科書と児童文学』(高文堂出版社、1995年9月)、府川源一郎「文学教材の傾向について」(『日本児童文学』第43巻第3号、1997年6月)

